ここ数年、ブームともなっている「発酵食品」。
身の周りでは、発酵食品や発酵調味料を手作りする人も増えてきました。
ヨーグルトメーカーを使って自家製ヨーグルトを作ったり、麹を発酵させて塩麹を作ったり。
ブームの火付け役となったのは「腸活」。
コロナ禍以降、免疫力アップやストレスケア、健康志向の高まりから腸内環境を整える「腸活」が注目を集めています。
しかし実際は、ブームとなるずっと前から、「発酵食品」は私たち日本人の食文化として根づいています。
そして、世界に誇る「和食」の風味を表現するのは、ほかでもない「発酵調味料」です。
一概に発酵調味料と言っても、何があるのか?それぞれの種類や特徴は?
今回は、それらの疑問にお答えするほか、選び方や使い方、手作り方法まで徹底解説いたします!
発酵調味料とは?
発酵調味料とは、人間にとって有益な微生物が化学反応を起こし、食品に含まれる成分が分解されること、つまり「発酵」によって作られる調味料です。
そこで気になるのは、そんな微生物の存在。
食品の保存性を高めたり、旨味を引き出すこと、腸内環境を整えることなど、人間にとって嬉しい作用をもたらしてくれる微生物とは、どんなものがあるのでしょうか?
①麹菌
②乳酸菌
③酵母菌
④酢酸菌
この章では、上記について解説します。
①麹菌
「国菌」とも呼ばれ、日本の発酵食品を生み出す代表的な微生物。
驚くことに、なんと糸状菌(カビ)の一種です!
米を原料とした米麹、大豆を原料とした大豆麹、麦を原料とした麦麹などがよく使われます。
醤油や味噌、お酢やみりんなど、家庭でおなじみの調味料が作られる際にも必ず使われます。
塩味だけでなく、旨味や甘みを感じられるのは、発酵の過程で糖やアミノ酸が作られるからなんです。
②乳酸菌
約200種類も存在する細菌で、ブドウ糖や乳糖を分解し乳酸を作り出します。
ヨーグルトやヤクルトなどの飲料に含まれるイメージが強いかも知れませんね。
実は乳酸菌も、醤油や味噌などの調味料が作られる際に使われます。
種類によって特性が違うので、それぞれの食品に合った菌種が利用されます。
腸の働きを整える作用が注目されています。
③酵母菌
ブドウ糖をアルコールと炭酸ガスに分解する微生物です。
酵母と言えば、パン酵母やビール酵母などがイメージしやすいでしょうか。
醤油や味噌などの調味料を作る際には、乳酸菌と同様に醸造の過程で用いられます。
高濃度の食塩に耐性をもつ菌が使われます。
④酢酸菌
アルコールを酢酸に変える微生物です。
こちらは名前から想像しやすいですね!
お酢を作る際に欠かせない細菌です。
原料をアルコール発酵させ、そこに酢酸菌を加えることでお酢ができあがります。
原料がお米なら米酢、りんごならりんご酢、ワインならワインビネガーとなります。
微生物の働くチカラってすごいですよね!
特に国菌とも呼ばれる「麹菌」の存在感、和食文化への影響は大きそうです。
すでにいくつかの調味料が登場しましたが、ここからは、そんな「麹」が活きた日本の発酵調味料について詳しくみていきましょう!
日本の三大発酵調味料を知ろう!
和食の味を決める「醤油・味噌・酢」は、どれも長い年月をかけて発展してきた発酵調味料です。
ここでは、その起源や種類、伝統的な製法についてわかりやすく紹介します。
醤油
~保存食から食事を美味しくする調味料へ~
醤油の歴史を辿ると、その原型は、食品の保存を目的にした塩漬けだったことが分かります。
食料を塩で漬けたものを「醤(ひしお)」といい、日本では弥生時代に、魚を塩で漬けた「魚醤」があったとされています。
又、中国では紀元前800年頃から「醤」の存在が記されており、飛鳥時代に醤油の先祖である大豆を原料とした「穀醤」が伝わりました。
そして、鎌倉時代には、お坊さんが中国から持ち帰った「径山寺味噌」が広がり、その上澄みやたまり汁が美味しく、醤油の発祥につながったと言われています。
江戸時代には、人々の嗜好に合わせて、関東で濃口醤油、関西で淡口醤油が確立し、普及しました。

【醤油の種類】
①白醬油
愛知県発祥。
小麦を主原料とした琥珀色の醤油。
淡泊ながら甘みが強く、麹の香りが際立つ。
主に料亭などで使われる。
②淡口醤油
関西で生まれた色の淡い醤油。
濃口より約1割食塩が多く使用される。
お吸い物や炊き合わせなど、素材の色や風味を生かしたい料理に使われる。
③濃口醤油
最も一般的な醤油。
国内出荷数量の8割以上を占める。
塩味のほか、旨味、甘味が豊富で、酸味、苦味などもバランスよく含み、幅広い料理に使いやすい。
④再仕込醤油
諸味を搾ったままの生揚醤油に麹を入れて再び仕込んで造る醤油。
色・味・香りが濃厚で、「甘露醤油」とも呼ばれる。
⑤溜(たまり)醤油
主に東海など中部地方で造られる。
大豆を主原料とし、製法は味噌に近いものがある。
とろみと濃厚な旨味、特有の香りが特徴。
魚の臭みを消すためお刺身との相性が良く、加熱するときれいな照りが出るため照り焼きにも向く。
【醤油ができるまで】
①製麹(せいきく)~醤油の素となる麹づくり~
まずは、大豆を蒸し、小麦を炒って割るなどの原材料処理をおこないます。
つぎに、原材料に種菌を混ぜ、麹菌を育てます。
②発酵・熟成
麹を塩水と共に桶に入れ、1年以上など長い時間をかけて発酵・熟成させます。
麹菌の働きによって酵素が働き始め、原材料の分解が始まります。
その後、乳酸菌が増殖することで乳酸発酵が進み、酸性化すると、今度は酵母菌が増殖して酵母発酵が進みます。
ゆっくりと長い時間をかけて醸造することで深い色や味わいに変化していきます。
③圧搾
熟した諸味から、じっくりと醤油を搾りだします。
これが、「生揚醤油」と呼ばれる、酵母や乳酸菌が生きたままの醤油です。
基本的に流通はしないが蔵元で販売されることがあります。
④火入れ・ろ過
生揚醤油を加熱することで微生物の活動を止め、品質を安定させます。
また、火入れをすることで香ばしい香りや赤みが増すので、風味や色の調整をします。
最後は不純物を取り除くためにろ過をして、醤油が完成です!
「生(なま)醤油」は、火入れをせず、ろ過のみおこないます。
味噌
~おかずとしても調味料としても重宝された味噌~
醤油の原型は、塩漬け発酵食品の「醤(ひしお)」でしたが、実は味噌のルーツもほとんど同じところにあるのです!
ちなみに味噌の語源は、「未醤(みしょう)」=未だ醤油になっていない、というところから来ているのは面白いですね。
平安時代には、「味噌」と書かれた書物もあり、主に特権階級の人々が大豆発酵食品として食べ物につけたり、そのまま食べていました。
味噌汁が登場したのは鎌倉時代です。
また、室町時代に入ると農民たちが自家製の味噌を作るようになったことから庶民にも広がり、時代の変化と共に、地域性豊かな味噌が発展しました。

【味噌の種類】
味噌は、用いる麹の種類によって、大きく3つに分類されます。
①米味噌:米麹を使って造られた味噌。
②麦味噌:大麦や裸麦で造った麦麹で仕込んだ味噌。
③大豆味噌(豆味噌):大豆麹と大豆と食塩で仕込んだ全大豆仕込みの味噌。
さらに、醸造期間(発酵と熟成)の長短、使用する麹の割合などによってもいくつかの種類に分類されます。
たとえば、醸造期間が短いほど色調が薄くなり、「白味噌」や「淡色味噌」となります。
また、醸造期間が長くなると色調は濃くなり、「赤味噌」となります。
特に米味噌や麦味噌では、大豆に対する麹の割合が高いと、熟成期間が短くて済むので塩分濃度が少なくなるのに加え、麹からの糖分によって甘みが出て、「甘口味噌」となります。
逆に、塩分量が多く麹の割合が低いと「辛口味噌」となります。
さらに、米味噌では「甘口味噌」より甘い「甘味噌」という分類もあります。
【味噌の製法】
味噌のルーツは醤油とほとんど同じでしたが、実は、製造方法もよく似ているのです!
醤油は液体状の諸味で発酵させますが、味噌は、吸水させた大豆を蒸煮し、あらかじめ造った麹と塩を混合します。
仕込みから熟成、完成まで固体状という点が違いです。
【地域の代表的な味噌】
仙台味噌(宮城県)
米味噌の中でも、辛口の赤味噌に分類されます。
濃厚な味わいや強い香りが特徴です。
信州味噌(長野県)
代表的な米味噌です。
国内で生産される味噌の約5割を占めています。
辛口系で色は淡色。
米麹の熟成した旨味や、豊かな香りが特徴です。
江戸甘味噌(東京)
米麹を多く使用した甘味噌。
色は光沢のある茶褐色で赤味噌に分類されます。
こってりとした濃厚な甘みが特徴です。
西京味噌(京都)
京都の代表的な白味噌。
米麹を多く使用し、塩分が低く上品な甘みが特徴です。
熟成期間が短く、なめらかで白っぽいベージュ色。
九州麦味噌(九州地方)
麦麹を使用した、香ばしい香りが特徴の味噌。
色は白から淡い色のものが多く、南九州ではより甘みの強いものが好まれます。
八丁味噌(愛知県)
愛知県岡崎市発祥の、豆味噌を代表する銘柄です。
熟成期間が長く、色は黒みを帯びた濃い赤茶色。
濃厚な旨味や独特の風味が特徴で、甘みが少なく、渋みや酸味を含みます。
酢
~日本の寿司文化を形成した酢~
発酵調味料の中でも、酢の歴史はかなり古いことが知られています。
世界では酢の起源は紀元前5000年前まで遡ると言われますが、日本では、飛鳥時代の大化改新のとき、酒や醤(ひしお)、酢が造られたと書かれた文献があります。
米を原料とする米酢は、盛んに宮廷料理に用いられ、江戸時代には庶民にも広がりました。
江戸中期には酒粕を原料とした粕酢が考案され、江戸前の握り鮨が流行するのとともに、酢の需要が高まりました。

【食酢の種類】
米酢をはじめ、日本で主に使われる食酢は、その製法から「醸造酢」と呼ばれます。
そして、その醸造酢は主に3つのカテゴリーに分類されます。
①穀物酢
米が原料の「米酢」、米や小麦、とうもろこし、酒粕など穀物が原料の「穀物酢」に分けられます。
②果実酢
ブドウ果汁が原料の「ブドウ酢」、リンゴ果汁が原料の「リンゴ酢」、その他果実の搾汁が原料の酢があります。
③醸造酢(穀物酢・果実酢以外のもの)
その他、穀類や果実、野菜、その他農産物やはちみつ、アルコールを原料とした酢。
【米酢の3つの発酵工程】
①糖化
米麹、蒸した米、水を仕込み、麹菌の働きにより糖化する。
②アルコール発酵
そこに酵母を加えてアルコール発酵をおこなう。
③酢酸発酵
アルコール発酵が終わった諸味を圧搾・ろ過し、そこに酢酸菌を含む種酢を加えて酢酸発酵する。
熟成させたのち、米酢ができあがる。
【食酢の調理効果】
酢は、塩とともに最古の調味料です。
その最大の調理効果は酸味を加えることですが、実はそれ以外にも様々なメリットがある優秀な調味料なのです!
①殺菌・静菌作用
先ほどもお伝えしたように、酢は日本の寿司文化をつくったと言っても過言ではないですが、その理由として食品の腐敗防止作用が挙げられます。
冷蔵設備がなかった江戸時代に寿司が庶民の楽しみとなったのは、酢飯なしには語れません。
②塩分を抑える
醤油や味噌など、塩を多く使用する調味料は塩分が高いです。
酢酸は味の強さを高め、味覚の満足度を高める効果があり、減塩に効果があります。
③臭み抜き
海に面する日本は魚料理が豊富ですが、魚には特有の生臭さを感じる成分が含まれます。
他の調味料よりも圧倒的に酸性度が強い酢は、古くから魚の臭み消しとして重宝されました。
今でこそ発酵調味料は、健康志向の高まりから発酵食品としての栄養やその効果が注目されています。
その起源を辿ると、食品の保存から始まり発展する中で、食事をより美味しく食べるための調味料としての位置づけを確立したことがわかります。
地域性豊かな調味料からは、それぞれの地域でより美味しい風味を追求した、人々の「食への想い」が感じられますね。
みりんは発酵調味料?
本みりん・みりん風調味料・みりんタイプ(発酵調味料)の違いとは?
みりんと言えば、醤油や味噌、酢などと同様に、家庭でおなじみの調味料ですよね。
しかし、それらの調味料が原材料や麹の種類、製法の違いによって様々な種類があるのとは違って、スーパーに並ぶみりんは「本みりん」のほか、「みりん風」さらには「みりんタイプ」と書かれているものがあり、「え?本物ではないの?」と気になってしまうこともあるかもしれません。
ここでは、それぞれのみりんの違いについて解説します!

【本みりん】
日本独特の甘味のある酒類調味料で、伝統的な発酵調味料です。
これまでに出てきた調味料よりは少し歴史が浅いですが、室町時代にはみりんの原型にあたるものの醸造が始まり、戦国時代には甘い高級なお酒として飲まれていました。
江戸時代には蒲焼きやそばつゆなど様々な料理に使われるようになりました。
製法のポイントは、糖化と熟成です。
もち米を使用した米麹に、蒸したもち米と焼酎を加えて仕込みます。
米のでんぷんを糖化させ、長期熟成させることで甘みを生み出します。
区分:酒類
酒税:課税
アルコール度数:約14%
原材料:もち米・米麹・焼酎もしくは醸造アルコール
塩分:含まれない
【みりん風調味料】
戦中・戦後の米不足や食糧難の際に本みりんの製造が禁止されたため代替品として登場しました。
本みりんは酒類に分類され、製造の禁止が解かれた後も販売が制限されました。
酒屋でしか取り扱えなかったので販路を拡大するためや、高い酒税を回避するために製造が盛んになりました。
区分:食品
酒税:非課税
アルコール度数:1%未満
原材料:水あめなど糖類、米、米麹の醸造調味料、酸味料など
塩分:含まれない
【みりんタイプ(発酵調味料)】
本みりんと同様にアルコールを多く含み、その名も発酵調味料と名づけられていますが、製法が異なります。
米や米麹を発酵させた後に、糖類やアルコール、塩などの原料が添加されます。
大きな違いは、食塩を添加することで酒類に分類されなくなるという点です。
区分:食品
酒税:非課税
アルコール度数:10%前後
原材料:水あめなど糖類、米、米麹の醸造調味料、食塩、アルコールなど
塩分:2%前後
ご紹介した3つのみりんの違いには、社会的背景が大きく関わっていることがわかりました。
酒類調味料である本みりんが、規制や法律などの問題に直面したため、社会のニーズを満たすためや商業的な理由で、代替品が広く一般に広がりました。
身体に良い発酵調味料を選びたい方には、本みりんがおすすめですが、それぞれの特徴を理解して料理に活かすのも良いですね。
話題の麹調味料って何?
おすすめ麹調味料の作り方と活用法3選!
ここまでで、日本の伝統的な発酵調味料には、全て「麹」が関わっていることがわかりました。
改めて、麹の持つチカラは偉大なものだと感じます!
市販されているそれらの発酵調味料を使うだけでも、健康的で美味しい料理を作ることができますが、麹がそのまま活きた「麹調味料」を活用することで、さらに様々な健康・美容効果を得られたり、旨味が引き立つワンランク上の料理を簡単に作ることができます。

麹調味料を手作りしよう!
少し手間をかければ、米麹や麦麹など、「麹」そのものを手作りすることも可能ですが、麹はスーパーや地域の味噌屋さん、麹店などで気軽に購入することができます。
ここでは手に入れた麹を使って簡単に作れるおすすめ麹調味料をご紹介します!
甘麹
<材料>
米麹:300g
60℃くらいの湯:500ml
<作り方>
①しっかりとほぐした米麹を炊飯器に入れ、お湯を加えてよく混ぜる。
②ぬれ布巾をかけたら、蓋をあけたまま保温モードにする。1~2時間ごとにかき混ぜ、60℃程度を保ちながら6〜8時間保温する。
③麹が甘くてやわらかくなったら完成。清潔な容器に入れて冷蔵庫で保管する。
醤油麹
<材料>
米麹:200g
醤油:250ml
水:100~120ml
昆布(5cm角):1枚
<作り方>
①しっかりとほぐした米麹、全ての材料を清潔な容器に入れ、よくかき混ぜる。
②常温で7日~10日おく。毎日清潔なスプーンでかき混ぜる。
③麹がやわらかく、甘い香りがしてきたら完成。冷蔵庫で保管する。
玉ねぎ麹
<材料>
玉ねぎ:1個
米麹:玉ねぎの30%の重量
塩:玉ねぎと麹の10%の重量
<作り方>
①清潔な容器に米麹と塩を入れ混ぜる。
②玉ねぎをフードプロセッサーで攪拌するか、すりおろし、①に加えて混ぜ合わせる。
③常温で約7日間おく。清潔なスプーンで毎日かき混ぜる。
④全体が溶けて、コンソメのような香りがしてきたら完成。冷蔵庫で保管する。
上記3つの麹調味料は、炊飯器や常温で発酵させることで簡単に作ることができますが、ヨーグルトメーカーを使って作るとさらに便利で時短にもなるので手軽にチャレンジできますよ。
どうやって使うの?活用法3選!
麹調味料が意外と簡単に作れることはわかりましたが、いったいどうやって使えば良いのでしょうか?
麹ならではの旨味や効果が活かせる活用法をお伝えします!

①漬ける
1つめのおすすめ活用法は、食材を「漬けこむ」ことです!
肉×麹調味料
お肉を1時間~ひと晩漬けこむことで、肉の旨味を引き出してくれるほか、肉のタンパク質が分解されるので食感がやわらかくなります。
下味がしっかりつくので調理の手間も省けます。
魚×麹調味料
お魚も麹調味料ととても相性が良い食材です。
魚本来の繊細な風味を活かしつつ、生臭さを取り除いてくれるのでより美味しく、ワンランク上の料理が作れます。
漬けておけば、あとは焼くだけ、煮るだけなど調理も簡単に。
さらに、お豆腐やゆで卵などを漬ければ絶品のおつまみに。
野菜を漬けこめば美味しくて塩分も控えめなお漬物ができあがります。
②混ぜる
基本の麴調味料があれば、その他の調味料やスパイス、オイルなどと混ぜ合わせてオリジナルの調味料が無限に作れます。
甘麹×スパイス
甘麹にお好みの味噌、韓国産粉末唐辛子、塩を混ぜたら自家製コチュジャンができあがります。
醤油麹×オイル
旨味成分(グルタミン酸)が豊富な醤油麹は、単純にお好きなオイルと混ぜ合わせるだけで立派なドレッシングとなります。
お好みでお酢や香味野菜のすりおろしなどを加えても◎。
玉ねぎ麹×トマト
コンソメのような香りが特徴の玉ねぎ麹は、洋食の味付けにも大活躍!
トマトピューレを混ぜて、醤油や塩、はちみつ、酢、スパイスなどでお好みの味にととのえたら、麹ケチャップのできあがりです。
③基本調味料のかわりに
3つめの活用法は、最もシンプルです。
麹の発酵により深い旨味を含む麹調味料は、食材にかけるだけや、そのまま味わってもとても美味しいです。
塩や砂糖など基本調味料のかわりにすると、塩分を抑えたい場合や、身体に良い甘味料を使いたい方にも役立ちます。
■卵かけごはんに、醤油のかわりに醤油麹をかける。
■煮ものに、白砂糖のかわりに甘麹を使う。
■スープを作る際、ほんだしやコンソメではなく、玉ねぎ麹を使う。
このように、麴調味料には魅力がたっぷりです!
食材の旨味を引き出してくれるだけでなく、簡単にオリジナル調味料が作れることで料理のレパートリーが広がります。
旨味成分のほか、ビタミンや食物繊維、オリゴ糖など栄養素も多く含むので、健康的な食生活を支えてくれます。
意外と簡単に作れることも魅力のひとつなので、ぜひ生活の中に「麹調味料作り」を取り入れてみてくださいね。
発酵調味料の選び方
発酵に興味を持たれている方は、美味しさだけではなく、健康や美容を気にかけて、身体に良いものを取り入れたい、という方も多いのではないでしょうか?
ここでは、身体に良い伝統製法の発酵調味料の選び方をご紹介します!
醤油編
①本醸造もしくは天然醸造と書かれたもの
②原材料が「大豆・小麦・食塩」のみでアルコールや添加物が入っていない
③国産の丸大豆が使われているもの
④木樽による熟成
味噌編
①天然醸造や自然醸造のもの
②原材料が「大豆・米(麦味噌なら麦)・食塩」のみでだしや添加物が入っていない
③国産大豆または有機大豆が使われている
④酵母や酵素が生きる「生味噌」である
お酢編
①伝統的な「静置発酵」で造られたもの
②国産米が使われているもの
③木樽による熟成
みりん編
①みりん風調味料やみりんタイプではなく「本みりん」を選ぶ
②さらにこだわるなら原材料が「もち米・米麹・本格焼酎」のみの伝統製法のもの
しかし、上記はあくまで無添加やより上質なものにこだわりたい方に向けた選び方なので、必ずしも無添加や伝統製法のものを選ぶ必要はありません。
国内で製造される調味料に含まれる添加物は、国が安全性を認めたものだけです。
地域性豊かな発酵調味料は、それぞれの地域で求められる味を引き出したり、料理を引き立てる製法や原材料が使われています。
特性を理解した上で、目的や好みに合ったものを選ぶのが大切です!
実際に使ってみよう!
旨味を引き出す発酵レシピ5選
いよいよここからは、発酵調味料を料理に活用してみましょう!
今回は、メイン(お肉料理)とスープ、副菜3品を献立にしてご紹介します。
鶏むね肉のしっとりソテー
~マスタード味噌ソース~
<材料>
鶏むね肉:1枚
・甘麹:大さじ2
・塩麹:大さじ1.5
米油:大さじ1
〔マスタード味噌ソース〕
味噌:大さじ1
粒マスタード:小さじ1
甘麹:小さじ1
(山椒の葉:あれば)
<作り方>
①鶏むね肉を2cm幅にそぎ切りし、余分な水分を取り除く。
②甘麹と塩麹を混ぜ合わせ、鶏肉の両面に塗り一晩漬けおきする。
③マスタード味噌ソースの材料を混ぜ合わせ、ソースを作っておく。
④フライパンに米油を熱し、漬けおきした鶏肉の両面を焼く。焼き色がついたら、蓋をして蒸し焼きにして中まで火を通す。
⑤皿に盛りつけ、マスタード味噌ソースを表面に薄く塗り、山椒の葉を添える。
キャベツとスプラウトの磯和え
<材料>
キャベツ:150g(4枚)
スプラウト(紫スプラウトなど):50g
あおさ:大さじ1
塩麹:小さじ1
レモン汁:大さじ2
お好みのオイル:適量
<作り方>
①千切りにしたキャベツを塩もみする(分量外の塩少々)。
②キャベツがしんなりしたら、スプラウト、あおさ、塩麹、レモン汁を加え混ぜ合わせる。
③オリーブオイルや亜麻仁油など、お好きなオイルをまわしかける。
かぼちゃとナッツのミネラルサラダ
<材料>
かぼちゃ:200g
ミックスナッツ:20g
鯖水煮:80g
・豆乳ヨーグルト:大さじ1
・味噌:小さじ1
・玉ねぎ麹:小さじ1/2
・亜麻仁油(またはオリーブ油):小さじ2
<作り方>
①一口大に切ったかぼちゃに、大さじ1の水とひとつまみの塩(分量外)をふりかけ、鍋に蓋をしてやわらかくなるまで蒸す。
②ミックスナッツは叩いて食べやすい大きさに砕き、①に加える。
③鯖水煮は汁気をきり、②に加える。
④ヨーグルト、味噌、玉ねぎ麹、オイルを加えて全体を混ぜ合わせる。
なすの麹照焼き
<材料>
なす:1本
・醤油麹:大さじ1
・バルサミコ酢:大さじ1
・本みりん:小さじ1
米油:大さじ2
片栗粉:適量
<作り方>
①醤油麹とバルサミコ酢、本みりんを混ぜ合わせておく。
②なすを2cm幅の輪切りにし、切り口に格子状の切り込みを入れる。切り口に片栗粉をはたく。
③フライパンに米油を熱し、茄子の両面を焼く。
④焼き色がついたら、①をまわしかけて、さっと絡める。

ブロッコリーの豆乳ポタージュ
<材料>
ブロッコリー:70g
玉ねぎ:60g
豆乳:200ml
水:100ml
甘麹:大さじ2
味噌:大さじ1
<作り方>
①鍋に子房にカットしたブロッコリー、薄切りにした玉ねぎ、水大さじ2と塩少々(分量外)を入れ、蓋をして弱火で蒸す。
②水200mlを①に加え、弱火でひと煮立ちさせる。豆乳と味噌を加え沸騰しないようにしながら温める。
③ミキサーやハンドブレンダーで攪拌し、なめらかにする。再度軽く温めても、冷製でも良いです。(冷製の場合は味噌を気持ち多めにすると良いです。)

発酵調味料を活用することで、手間や多くの時間をかけなくても、季節の献立がテーブルを彩ってくれます。
食材の風味を引き立ててくれるので、シンプルな調理法や同じ味付けでも、食材を変えるだけでレパートリーが広がります。
今回は献立形式で5品をご紹介しましたが、こちらを参考例として、ぜひお好きな食材・お好きな発酵調味料を使って試してみてくださいね。
まとめ
■発酵調味料とは、日本ならではの「麹菌」と共に長い歴史の中で発展してきた地域性豊かな伝統調味料!
世界に誇る「和食」文化形成の立役者
■手作り可能な麹調味料は、旨味と栄養の宝庫!
手軽に使えて料理をランクアップしてくれる頼れる万能選手
■発酵調味料は、伝統製法のものがおすすめ!
それぞれの特徴を理解し、作りたい料理や好みなど目的に合ったものを選ぶことが大切
いかがでしたでしょうか?
今回は、発酵調味料の起源から製法、種類、選び方や活用方法までたっぷりとご紹介させていただきました。
2013年に和食がユネスコの無形重要文化財に登録された背景にも、発酵調味料の存在があったことがうかがえます。
そんな魅力的な日本の発酵調味料を、ぜひ日々の食生活に取り入れ、時には調味料を手作りしたり楽しみながら活用してみてくださいね。

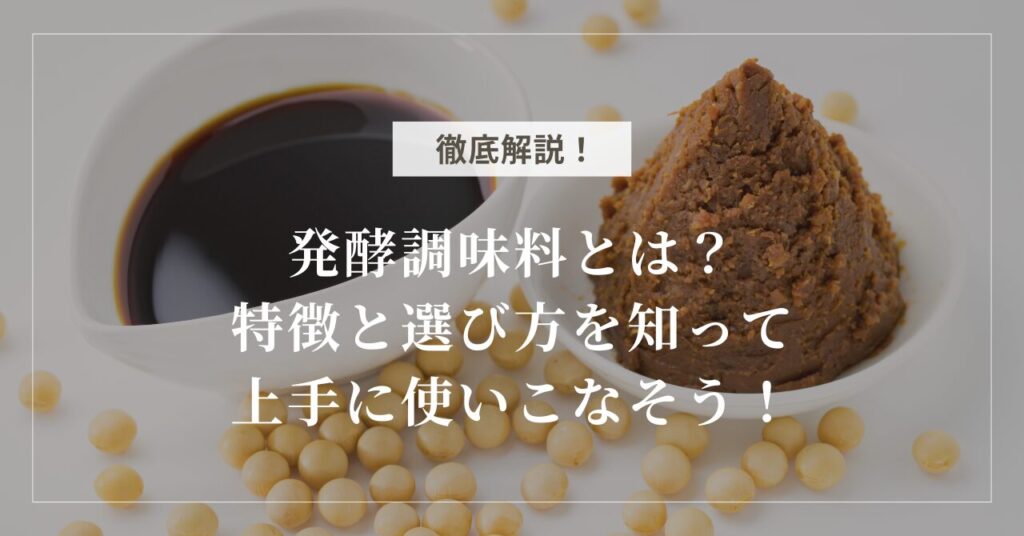

コメント